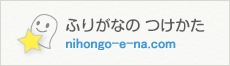涼しさを聞く
35℃を超える日も多い日本の夏。多くの日本人は風鈴の音を聞くと涼しさを感じる。そんな風鈴を20年以上作り続け、そして、今では珍しい風鈴の屋台をひいて町を練り歩く風鈴職人がいます。
富士山の南東に位置する三島市。古くから宿場町として栄えたこの町には、富士山からの美しい湧き水が町のあちこちを流れている。真夏でも手をつけると冷たい。公園や遊歩道なども整備されていて、暑い季節には子供たちや親が涼を求めて木々に囲まれた水辺に集まってくる。
冷たく澄んだ水とひんやりとした緑の木陰。そんな町中の一角で耳を澄ましていると、子供の歓声と蝉の鳴き声に混じり、シャラリンチャリンと、遠くから涼しげで心地よい音が近づいてくる。三島の夏の名物、風鈴の引き売りだ。屋台には30個ほどのガラスの風鈴が、逆さになったワイングラスのように吊り下げられている。丸かったり細長かったり、富士山やスイカの絵があったり、何も描かれていなかったりと、形もデザインもさまざま。全く同じものは一つもない。風が吹くたび、屋台が動くたびにそれらの風鈴が一斉に揺れ、シャラリンチャリンと音を奏でる。
東京から観光に来たという親子連れが、屋台に寄ってきた。「涼しそうな音ですね。家にあるドアベルと違って、風鈴の音は自然な感じがします」
「涼しい思い出」を届けたくて
屋台を引いて歩いているのは、風鈴職人の関根久雄さん。つげ笠をかぶり、法被と股引を身に付けたスタイルで、ゆっくりと町中を歩く。毎年夏の6月初めから8月の末まで、風鈴の引き売りをしている。
「この屋台、実は風鈴を売るのが一番の目的じゃないんです。三島に来てくれる人たちに、涼しい思い出を持って帰ってもらえればと思って始めたんです。町の中をたくさんの風鈴が通りすぎる風景と音、涼しそうだと思いませんか。そして、また、夏にどこかで風鈴の音を聞いたとき、三島の町を思い出してもらえると、うれしいなと思って」
今では三島の夏の風物詩になっている風鈴の屋台。
「引き売りを始めて20年になるんですが、最近は車と並んで信号待ちをしていると、エアコンが効いているのに、わざわざ車の窓を開けてくれる人がいるんです。風鈴の音で涼しさを味わいたいって。なんだか、気持ちが伝わったようで、うれしいです」と関根さんは笑顔で話す。
こだわるのは「自然な音」
関根さんの家は陶器店で、風鈴は独学で作り始めた。もともと古代ガラスに興味を持って研究を始めたのがきっかけで、三島に名物を作りたいと思ったとき、風鈴を思いついたという。清らかな湧き水と風鈴の涼しさのイメージが重なったそうだ。透明感の漂う代表的な作品の「鹿の子」は、この湧き水の動きを表現した風鈴だ。今では、関根さんの作る「みしま風鈴」は、三島市の特産品である「みしまブランド」に認定されている。
関根さんがこだわっているのは「自然な音」だ。「自然な音」というのは、関根さんによると生活の中に溶け込んでいる音、何気なく耳に入る音、邪魔にならない音、自己主張しすぎない音ということになる。
「風鈴が鳴って、感じて欲しいのは涼しさです。風鈴が鳴ると、あ、風が吹いているなと感じてもらいたい。そのためには、風鈴の音が大きすぎると、風鈴自体の主張が強くなりすぎて、うるさい音になってしまいます。音が低い場合も、グラスを叩いたときのような打撃音になってしまい、涼しい風がイメージしにくくなってしまいます」
ガラスと対話しながら工夫を重ねる
関根さんの工房は自宅3階にある。風鈴の胴体作りはすべて一人でこなし、工程も同業者が驚くほどシンプル。それでも質の高いガラスが作れるのは、関根さんいわく「ガラスに無理をさせずに、ガラスのなりたいようにさせるから」。制作側の都合に合わせるのではなく、ガラスの状態を見ながら、まるでガラスと対話するように作っていくのだという。だから、大量生産はできない。
関根さんは、より「自然な音」になるようにガラスにいろいろな金属を加えるなど、毎年新しい技術に挑戦し続けている。材料選びだけでなく、風鈴の形や短冊の長さなども変えて、音の大きさや高さ、音質について試行錯誤を繰り返す。涼しさを伝える工夫は音だけではない。風鈴に富士山の絵を描くのも、三島から富士山が見えるからだけではなく、富士頂上の涼しさをイメージしてほしいからだと言う。
「形や大きさ、材質、デザインなど風鈴のすべての要素に意味や意図があるんです。涼しさが伝えられるなら、どんな工夫でもするし、まだまだいいものができると思う。今までで一番上手くできた風鈴はどれかとよく質問されるんですが、いつも、1ヵ月後に作る風鈴ですって答えるんです」
「日本の夏」を伝えたい
関根さんは日本の文化としての風鈴、そしてガラスの面白さを伝えるために子供たちに風鈴作りの体験教室を開いている。子供たちを指導していて気付かされたことがあるという。「以前は同じ形、同じ音の風鈴を作ることを目指していたんです。でも、子供たちが一所懸命作ってできあがるいろいろな風鈴を見ていたら、風鈴にも個性があっていいんじゃないかって思えたんです。ガラスは少しでもひびがあったり、いびつだったり、空気の泡があると不良品とされてしまう。でも、陶器だとそれが味わいと受け止められたりすることがあるでしょう。ガラスも陶器のように見てもらえるようになれば、楽しみ方や可能性がもっと出てくるんじゃないかと。もちろん、プロとしての技術があった上での話ですが」それ以来、質の高い風鈴を目指すことに変わりはないが、一つ一つの作品の個性を楽しめるようになったという。
風鈴の屋台を引いて町を歩いていると、母子連れに出会うことがある。そんなとき、母親は子供に向かって、「ほら、風鈴よ。涼しそうね」と話しかけるという。たとえそれが、まだ言葉を解さない赤ん坊であったとしても。その様子を見て、関根さんは安心を覚えるという。富士山を源に地下を流れて湧き出し続ける水のように、「日本の夏の音」は、これからも親から子へ脈々と受け継がれていくのだろう。